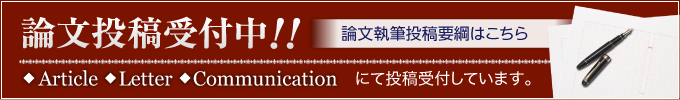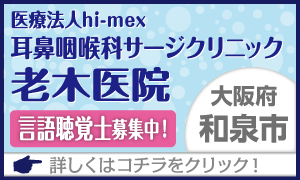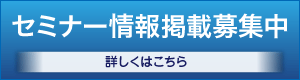大腿骨頚部骨折患者における床での立ち座り練習が転倒自己効力感や身体能力に与える影響

2)日高リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター
3)日高病院 回復期リハビリ室
【はじめに】
近年、転倒に関する心理的影響として転倒恐怖が注目されている。この転倒恐怖に対し、床上動作能力との関連1)や日常生活動作練習を実施した報告2)が散見されるが、床での立ち座り練習との関連を報告したものは少ない。そこで我々は、予備検討として、床での立ち座り練習の実践が転倒自己効力感の向上に関連するか、反復型実験計画(ABA型デザイン)を用いて検証した3)。結果、転倒自己効力感に肯定的な影響を与えていることが示された。
床での立ち座り練習は、転倒恐怖の対象である床との距離を能動的に近づける行動であり、その行動を反復し体験することが各活動に対し転倒することなく、動作を遂行する自信に繋がるのではないかと考えた。更に、上下の大きな重心移動から得られる筋力の賦活やバランス向上など身体面への効果も期待され、転倒自己効力感や身体能力の向上に寄与するのではないかと考えた。
これらを踏まえ今回、対象者数を複数名とし、床での立ち座り練習が転倒自己効力感の向上に寄与するか、他の身体能力の評価も含めて検証した。
【対象】
転倒にて受傷した大腿骨頚部骨折患者7名を対象とした。対象者は全て、全荷重が可能な者、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)が21点以上とした。骨粗鬆症の診断を受けている者、転倒恐怖が無い者は除外した。対象者の内訳は、男性2名、女性5名(平均年齢70.7±10.3歳)であった。受傷してから当院入院までの平均日数は29.7±14.7日であった。対象者には、本研究の目的および方法に関する十分な説明を行い書面にて同意署名を得た。
【方法】
理学療法を1日3~5単位実施している7名の対象者に、床での立ち座り練習を1日の理学療法中に15~20分施行した。介入期間は5日間とし、開始時期は入院後2週間以内もしくは全荷重開始後2週間以内とした。床での立ち座り練習の定義は、静的立位から床に座る、静的床座位から立位となることとした。その際、立ち座りのために必要とする手支持台の有無は問わず、介助に関しては最小限とした。
評価項目は、転倒恐怖の量的な評価としてModified Falls Efficacy Scale(MFES)4,5)(表1)を用い、身体能力評価はBerg Balance Scale(BBS)、Timed Up and Go Test(TUG)、10m最大歩行速度(10m Maximum Walking Speed;10MWS)とし、測定者は担当理学療法士とした。測定時期は介入前と5日間の介入後の計2回とした。
統計学的処理は、介入前後の比較をするため、MFES、BBSにはWilcoxonの符号付順位検定を、TUG、10MWSには対応のあるt検定を行った。統計解析ソフトはDr.SPSSⅡfor Windowsを用い、有意水準は5%とした。
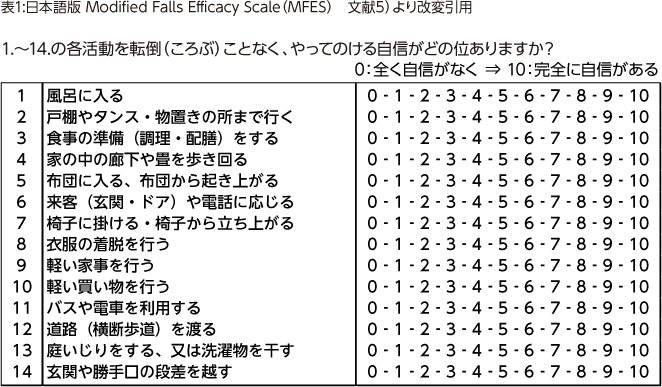
【結果】
介入前の中央値(範囲)は、MFESが66.0(37-130)点、BBSが54.0(50-56)点、平均(標準偏差)は、TUGが11.6(3.3)秒、10MWSが61.9(17.7)m/minであった。介入後の中央値(範囲)は、MFESが107.0(82-133)点、BBSが55(53-56)点、平均(標準偏差)は、TUGが10.1(3.09)秒、10MWSが75.5(15.9)m/minであった。
介入前後でMFESが向上した者は6名であり、その変化点は75点、41点、20点、9点、9点、1点であった。低下した1名の変化点は-19点であった(表2)。また、MFESが介入後に低下した1名については担当理学療法士にヒアリングしたところ、対象者がイメージしていたよりも円滑に床での立ち座り動作を遂行することができなかったため、後ろ向きの感情を抱いてしまったとのことであった。
MFESは有意差を認めなかったが、MFESの効果量(r)は0.64であった(表3)。介入前後の比較では、10MWSのみ有意差を認めた(p<0.05)(表3)。
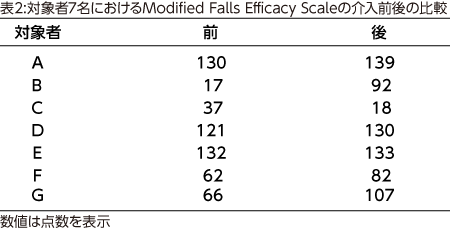
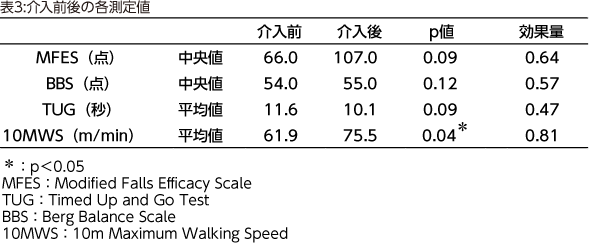
【考察】
介入前後でMFESが向上した6名の中で、介入前のMFES得点が70点以下の対象者の殆どは介入後にMFESの得点が向上し、更に、床での立ち座り練習がMFES得点において大きな効果量を示したことから、このような対象者には床での立ち座り練習の実践が有効ではないかと考えられた。今回、有意差を認めた10MWSにおいては筋力と相関関係があるとされ6)、床での立ち座り練習の反復が、歩行に必要な筋群を賦活させた可能性が考えられた。しかし、筋力における定量的な評価は実施しておらず、推測の域を超えない。また、対象者数が少ないことや、通常理学療法の具体的内容が考慮されていないことも挙げられ、本研究の限界と考えられた。
Bandura7)によると自己効力感を高めるには、4つの情報源があるといわれており、それらは、実際に経験する「遂行行動の達成」、他人の行動を観察する「代理的体験」、自己教示や他者からの説得によって行動できると思いこませる「言語的納得」、行動を起こさせるような情動を喚起する「情動的喚起」といったものでありこの情報源は自ら作り出していくものといわれている。特に「遂行行動の達成」に関する情報が自己効力感を高める最も強力な情報であると言われ、理学療法においても適切な運動課題や目標設定により自己効力感の向上や身体能力の向上に寄与できる可能性が考えられた。
●参考文献
1)Nomura T,et al:Preliminary study of the relationship between fear of falling and ability to sit on the floor. J Phys Educ Med,11:19-26, 2010.
2) 鈴木哲・他:Fall Efficacy Scaleの評価結果をもとにしたADLおよびIADL訓練によって入院高齢患者の転倒恐怖感を軽減できるか?. 理学療法科学,25(6):987-994 ,2010.
3)大谷知浩・他:床での立ち座り練習が転倒自己効力感に与える影響.第31回 関東甲信越ブロック理学療法士学会(会議録).
4)Hill KD,et al:Fear of falling revisited.Arch Phys Med Rehabil.77(10);1025-1029,1996.
5)近藤敏・他:高齢者における転倒恐怖.総合リハ,27(8):775-780,1999.
6)諸橋勇・他:最大歩行速度 臨床評価指標入門.内山靖・小林武・潮見泰藏 編.協同医書出版社,pp127-133,2003.
7)Bandura, A:Self-efficacy The exercise of control.New York:W.H.Freeman and Company,pp79-113,1997.